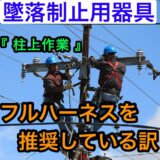こんにちは! まひろでーす!
2022年 1月2日より、フルハーネスの着用義務化が始まりましたね。
今回は、墜落制止用器具の「第一種」と「第二種」の違いについて、まとめました!
違いや見分け方がわかれば、作業環境にあった墜落制止用器具を使って、安全に作業することができます。
「第一種」「第二種」の確認方法は、ショックアブソーバを確認しましょう!
墜落制止用器具の「第一種」、「第二種」というのは、ショックアブソーバの事なんです。
ショックアブソーバは、墜落を制止するときに生じる衝撃を、緩和するための器具です。
また、墜落制止用器具を安全に使う上で、とても大事な情報が記載されています。
それぞれの違いや、見分け方がわかれば、作業環境に合った墜落制止用器具を選べますよ!
ちなみに、「ショックアブソーバー」って、語尾を伸ばしたくなりますが、(私だけではないはず )
JIS規格には、「ショックアブソーバ」と書いてあります…
でっ?って話なんですが、一応。
それでは早速ご紹介します!
「第一種」と「第二種」の説明、見分け方、選び方について。
前述の通り、「第一種」や「第二種」というのは、ショックアブソーバの種別の事を言います。
ショックアブソーバは、主にランヤードに付いています。
墜落を制止するときに生じる衝撃を、緩和するための器具です。

第一種ショックアブソーバの説明
「第一種」とは、自由落下距離 1.8mで、墜落を制止するときの衝撃荷重が4.0kN以下になる機能を備えた、ショックアブソーバをいいます。
( 4.0kN = 408kgf )
また、第一種ショックアブソーバが備わっているランヤードの事を、タイプ1 といいます。
腰より高い位置にフックを取り付けて使用することができます。
第二種ショックアブソーバの説明
「第二種」とは、自由落下距離 4.0mで、墜落を制止するときの衝撃荷重が6.0kN以下になる機能を備えた、ショックアブソーバをいいます。
( 6.0kN = 612kgf )
また、第二種ショックアブソーバが備わっているランヤードの事を、タイプ2 といいます。
第一種とは違い、腰より低い位置、足元付近の高さといった位置でもフックを取り付けて使用することができます。
「第一種」、「第二種」の見分け方
「第一種」、「第二種」の見分け方については、ショックアブソーバの 「種別」 を確認してみましょう。
写真のショックアブソーバは、左下部に記載があります。

「第一種」、「第二種」の選び方
次に選び方です。
作業環境によって、ランヤードのフックをかける位置が様々ですよね。
フックをかける位置で、「第一種」or「第二種」のどちらにするかを選びます。
第一種:腰より高い位置
第二種:腰より低い位置、足元付近にも掛ける場合
第二種は足元付近にもフックを取り付けることができますが、その分、墜落の際に落下距離が伸びてしまいます。
基本的には第一種を選び、腰より高い位置にフックを掛け、落下距離を少しでも短くすることが大切です。
ショックアブソーバに書かれている重要情報
他にもショックアブソーバには、様々な情報が書かれています。
確認ポイントは次の5つ
・【種類】フルハーネス or 胴ベルト
・【種別】第一種 or 第二種
・【最大自由落下距離 】距離の記載
・【落下距離】距離の記載
・【使用可能質量】100kg or 130kg
以上の理由から、ショックアブソーバの種類としては、以下の6種類になります。
- フルハーネス型 第一種 100kg
- フルハーネス型 第一種 130kg
- フルハーネス型 第二種 100kg
- フルハーネス型 第二種 130kg
- 胴ベルト型 第一種 100kg
- 胴ベルト型 第一種 130kg
6種類それぞれ写真を撮りましたので、一緒に確認してみましょう!
フルハーネス型 第一種ショックアブソーバ
使用可能質量が、100kgと130kgの2種類あります。
- 【種類】フルハーネス型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【使用可能質量】100kg

- 【種類】フルハーネス型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【使用可能質量】130kg

フルハーネス型 第二種ショックアブソーバ
第二種も、使用可能質量が100kgと130kgの、2種類あります。
- 【種類】フルハーネス型
- 【種別】第二種(6kN)
- 【使用可能質量】100kg

- 【種類】フルハーネス型
- 【種別】第二種(6kN)
- 【使用可能質量】130kg

胴ベルト型 第一種ショックアブソーバ
胴ベルト型も、使用可能質量が100kgと130kgの、2種類あります。
- 【種類】胴ベルト型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【使用可能質量】100kg

- 【種類】胴ベルト型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【使用可能質量】130kg

胴ベルト型は、「第二種」のショックアブソーバがありません。
「第一種」しかない為、腰より高い位置にフックを掛けて使用することになります。
ショックアブソーバの他にも、「第一種」と「第二種」はあるの?
ショックアブソーバ以外にも、「第一種」or「第二種」といった違いはあるのでしょうか。
それぞれ確認していきましょう。
フルハーネスは?
フルハーネス本体に第一種、第二種はありません。
ランヤードは?
ランヤードについているショックアブソーバが、第一種 or 第二種 どちらになっているかを確認してください。
結局、ショックアブソーバの確認になります。
墜落制止用器具は?
墜落制止用器具というと、一般的にはフルハーネスとランヤードのセットという事になるかと思います。
ということで、結局チェックするポイントとしては、こちらもランヤードのショックアブソーバが、第一種 or 第二種かをチェックすればOKです。
胴ベルト型は?
胴ベルト型の墜落制止用器具は、第一種のみです。
ランヤードのフックは腰より高い位置に掛けて使用します。
「墜落制止用器具」は、作業環境を確認して選びます!
墜落制止用器具は、地面から作業床の高さと、墜落制止用器具の落下距離を確認して選びます。
「地面から作業床の高さ > 落下距離」の状態にすることで、地面に衝突する前に、墜落を制止することができます。
地面から作業床の高さを確認します。
はじめに、地面から作業床までの距離を確認。
次に、ランヤードのフックを掛けることができる場所を確認します。
墜落制止用器具を決めます。
地面から作業床までの高さ、フックを掛ける位置の確認が終わったら、墜落制止用器具を決めます。
基本的には、フルハーネス型を選びます。
作業床までの高さが、2.0mから6.75m以下までは胴ベルト型も使用することができます。
ランヤードを決めます。
ランヤードは、前述した5つのポイントを元に説明していきます。
・【種類】フルハーネス or 胴ベルト
・【種別】第一種 or 第二種
・【最大自由落下距離 】距離の記載
・【落下距離】距離の記載
・【使用可能質量】100kg or 130kg
【種類】フルハーネス型 or 胴ベルト型
墜落制止用器具をフルハーネスを選んだ場合、「フルハーネス型ランヤード」。
胴ベルトを選んだ場合、「胴ベルト型ランヤード」を選びます。
【種別】第一種 or 第二種
今回の記事テーマ、「第一種」「第二種」どちらを選ぶか問題!
先程確認した、ランヤードのフックを掛ける位置が腰より高い位置の場合、「第一種」。
腰より低い位置、足元付近にも掛けることがある場合、「第二種」を選びます。
【落下距離】
ショックアブソーバに記載してある「落下距離」を確認し、「地面から作業床の高さ> 落下距離」になるランヤードを選定します。
詳しくは、こちらの記事をどうぞ!
【使用可能質量】
使用可能質量とは、自分の体重と腰道具の装備品の合計です。
- 使用可能質量 < 100kgの場合、100kg用
- 使用可能質量 > 100kgの場合、130kg用
フルハーネス型墜落制止用器具に、胴ベルト型ランヤードを使用してはいけません。(また、逆も然りです。)
【おすすめ】 フルハーネス用ランヤード「第一種」
ここからは、オススメのランヤードをそれぞれ紹介していきます。国内シェアトップを誇る藤井電工製品で選定していきます。
はじめに、フルハーネス用ランヤード「第一種」です。
「コルトリトラ」最短の落下距離で停止
引き出したストラップが、常に最短になる「常時巻取式」です。
万一の墜落時に、最短の落下距離で停止してくれます。
- 【種類】フルハーネス型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【最大自由落下距離】2.3m
- 【落下距離】2.9 ~ 4.4m
- 【使用可能質量】100kg
「ノビロン」伸縮自在・軽量・コンパクト
巻取型に比べて100グラム軽いです。
通常は短くなっているので、作業の邪魔になりにくいのもポイント!
- 【種類】フルハーネス型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【最大自由落下距離】2.3m
- 【落下距離】4.4m
- 【使用可能質量】100kg
【おすすめ】フルハーネス用ランヤード「第二種」
次に、フルハーネス用ランヤード「第二種」の紹介です。
「第二種」のショックアブソーバを備えたランヤードをタイプ2と呼びます。
「ノビロン」 タイプ2
巻取型は、タイプ2の製品がありません。
タイプ2は、ノビロンがオススメ!
タイプ1に比べて、最大自由落下距離、落下距離が長くなっているので要チェックです。
- 【種類】フルハーネス型
- 【種別】第二種(6kN)
- 【最大自由落下距離】4.0m
- 【落下距離】5.3m
- 【使用可能質量】100kg
【おすすめ】胴ベルト型ランヤード「第一種」
最後に、胴ベルト型ランヤード「第一種」を紹介します。
胴ベルト型も「ノビロン」
柱上安全帯用ベルト(ワークポジションニング用器具)に取り付けることで、墜落制止用器具として、使用できます。
胴ベルト型も同じく、「ノビロン」がオススメです!
- 【種類】胴ベルト型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【最大自由落下距離】1.8m
- 【落下距離】3.5m
- 【使用可能質量】100kg
【おすすめ】フルハーネス・胴ベルト兼用型
最後に、藤井電工の最新モデルを紹介します。
最新モデル!「EZリトラ」
フルハーネス型・胴ベルト型、2本も揃えたくない!という方に朗報です。
1本で2本分の役割です!価格は他モデルに比べて割高ですが、2本揃えることを考えると、かなりお得です!
しかもこのショックアブソーバは130kgまで対応しています。
- 【種類】フルハーネス・胴ベルト兼用型
- 【種別】第一種(4kN)
- 【最大自由落下距離】2.3m(フルハーネス)
- 【落下距離】3.2~4.5m(フルハーネス)
- 【最大自由落下距離】1.8m(胴ベルト)
- 【落下距離】2.5~3.7m(胴ベルト)
- 【使用可能質量】130kg
【まとめ】「第一種」or「第二種」違い・見分け方編 まとめ
今回は、「第一種」と「第二種」の違いや見分け方についてまとめてみました。
それぞれの違いが分かれば、作業環境に合った、墜落制止用器具を選べますよね!
作業環境や、装備品を含めた自分の体重に合う、墜落制止用器具を選定することが重要です。
足元にフックを掛けることはないのに、第二種を選定したり、大は小を兼ねると考え、本来なら100kg用で良いのに、130kg用を選定したり、といったことが、ないようにしましょう!
万一の墜落事故の際に、落下距離が伸びて、衝撃荷重が大きくなってしまいます。
金銭面においても……
第一種より第二種、
100kg用より130kg用の方が、
それぞれ価格が高くなります。
少しでも参考になれば幸いです。
墜落制止用器具についてもっと知りたい方、ご興味あれば下記の記事もぜひ!
また、もし不明な点があればお問い合せからご連絡ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!